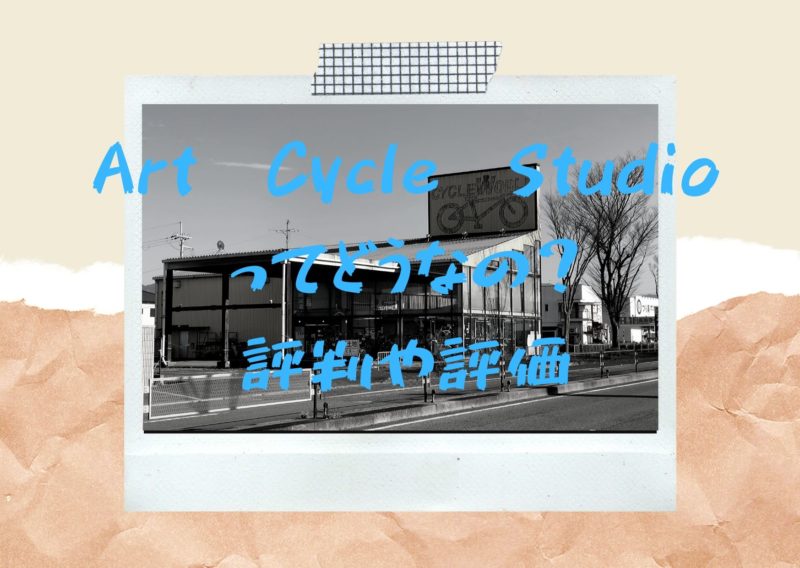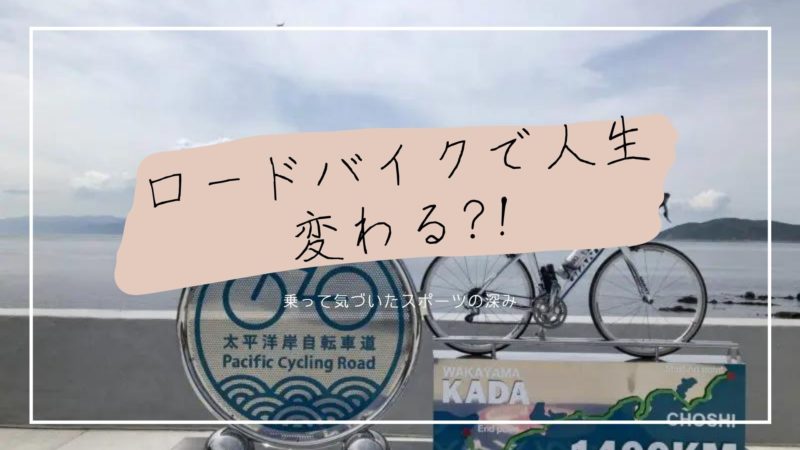2020年6月30日。
自動車の煽り運転の罰則化と同時に、自転車の道路交通法改正がなされ、自転車でも罰則が厳しくなりました。
自転車に関しては、マナーの悪さからうんざりしている、悩んでいるドライバーも少なくありません。
道路交通法改正がされた現在、実際改正された道路はどうなってしまったのか?についてお伝えします。
(注:筆者は大阪住みで、あくまで大阪の自転車状況を見たままお伝えします)
自転車の道路交通法改正範囲はどれぐらいだったのか

まずは自転車における道路交通法の違反行為がどれぐらいあるのか理解しなければなりません。
6月30日の改正前に存在した従来の危険行為は14項目
通行禁止違反
歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
通行区分違反
路側帯通行時の歩行者の通行妨害
遮断踏切立入り
交差点安全進行義務違反等
交差点優先車妨害等
環状交差点安全進行義務違反等
指定場所一時不停止等
歩道通行時の通行方法違反
制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
酒酔い運転
安全運転義務違反
この14項目から新たに加わるのが
妨害運転
です。
そして、この妨害運転の範囲は
- 逆走して進路をふさぐ
- 幅寄せ
- 進路変更
- 不必要な急ブレーキ
- ベルを執拗に鳴らす
- 車間距離の不保持
- 追い越し違反
の7項目が妨害運転として適用されるようになりました。
メジャーどころで言えば街中を車で走っていると良く見かけるのが逆走ですよね。
これが妨害運転の一つとして適用されることとなったわけです。(従来の範囲でも逆走は違反でしたが、更に罰則を強くした感じ)
そして、改正によるこの15項目を
14歳以上の運転手が
3年以内に2回危険行為として摘発された場合
安全講習を義務付けられるようになります。
受講しなかった場合、5万円以下の罰金が科せられます。
ちなみに受講料金も発生するので、結局摘発されたら受講料金を払うか5万円以下の罰金を払うかの選択肢は必ずくるということです。
交通法改正後、街はどうなった?

6月30日の道路交通法改正後、しばらく道路を走ってみましたが、
いつもと変わらない
でした。
逆走、進路妨害、傘差し運転、スマホ運転、なんでもあり。
年齢層もおばちゃん、おじさんから中高生、社会人と幅広い。
いつもと変わらない景色、一番驚きなのが警察がいても関係なしに行われている事です。
警察も注意しませんでした。
日常は何も変わらないのが実態です。
改正後でもなぜ変わらないの?
自転車の道路交通法改正が行われたにもかかわらず、現場のマナーが変わらないのは何故でしょう?
大きな理由に
- そもそも自動車免許を持っていない
- 交通法改正された事実を入手する方法がない
- 昔の乗り方で大丈夫だったから今も問題ないという認識
の三つが挙げられます。

こちらの記事でも取り上げたのですが、そもそもみんながみんな自動車免許を持っているわけではありません。
中には免許を取らずに歳を重ねた人もいますし、中高生といった免許を取得できない年齢層もいるわけです。
その事から、自転車ルールを教えてもらう場所が非常に少ない、中高生なら学校で指導されますが免許を取らずに重ねた主婦には教えられる場所がありません。
ママ友から「自転車の罰則が増えたらしいよ」くらい風の噂レベルなので、マナーが浸透するとは到底思えません。
そして何よりの理由が改正された事実を入手する方法がない事です。
新聞やテレビで細かく取り上げてくれれば、おじさんおばさん層でも認知しやすいですが、テレビですら抽象的かつ簡易的に取り上げるのが現状です。
このような実態から、改正された範囲なんかわかりませんし、今までも捕まった事がない人からすれば「いつもと変わらないだろう」と意識を向上させることができません。
何より入手できない事から、自分で調べて認識していくしかないのです。まるで日本の政治みたいに。
以上の事から、改正後も街に変わった光景を見ることはないですし、これからも変わらないんじゃないか?と思いますね。
何か起きてから、なのが今の自転車の現状
自転車の道路交通法改正は、あくまでドライブレコーダーによる悪質な自転車乗りがメディアでも取り上げられた事から、早急に対策した結果だと考えられます。
となると、警察側もちゃんと自転車の道路交通法を理解している人の方が少ないですし、何なら「私は部署が違うので管轄外です」と全く取り合ってくれない、無知識な警察だって存在するわけです。
この現状で改正されても、取締りを強化する方が珍しいと思いますね。
事実大阪で自転車の取り締まりの為に警察が交差点に立っていたりする光景を見たのは1回きりくらい、それも逆走とかは取り締まらずに二人乗りとか安易な部分のみです。
警察側も自転車を取り締まった所で点数稼ぎにならないし、手間が増えるだけなので、何か起きてから対応すると考えられます。
で、自転車事故の通報とかほぼないのが実態かと。
実際自転車事故って
- その場から逃走
- 大丈夫ですか?と声をかけてその場で処理
の二種類が非常に多いと思います。
おじさん同士の事故で片方は逃げたりするのを目の当たりにしてますし、おばちゃん同士なら怪我してるけど口喧嘩して冷静さを取り戻したら話して終わり。
イヤホンしてて無視とか。
警察を呼んで処理をしてもらうまでの工程があまりに遠いと思いますね。死亡事故とか救急車を呼ばないといけないレベルでないと動きません。
特に大阪は人情の街、事故ってテンパった時に余計に喋くりが出てくるので示談でおしまいが多い。
あくまで個人的な感想ですが、何か起きるまで待っている警察側と、何か起きても示談が多い自転車という手軽な乗り物のバランスが、自転車ルールの浸透から遠ざかっていると考えられます。
そう考えると講習まで辿りつく運転手って相当悪質なのかもしれません。
道路交通法改正を浸透させるには
自転車の道路交通法が改正された事に対し、自転車マナーを向上させる為にも
- 警察の交通安全週間
- 町会等で自転車講習を促す
といった手間をかけていかないと浸透しないなと思います。
日常のどこかで自転車のルールを組み込んでいかないと、現状は変わらないでしょう。
我々自転車乗りもあらかじめ調べて、意識の向上に励むしかありません。